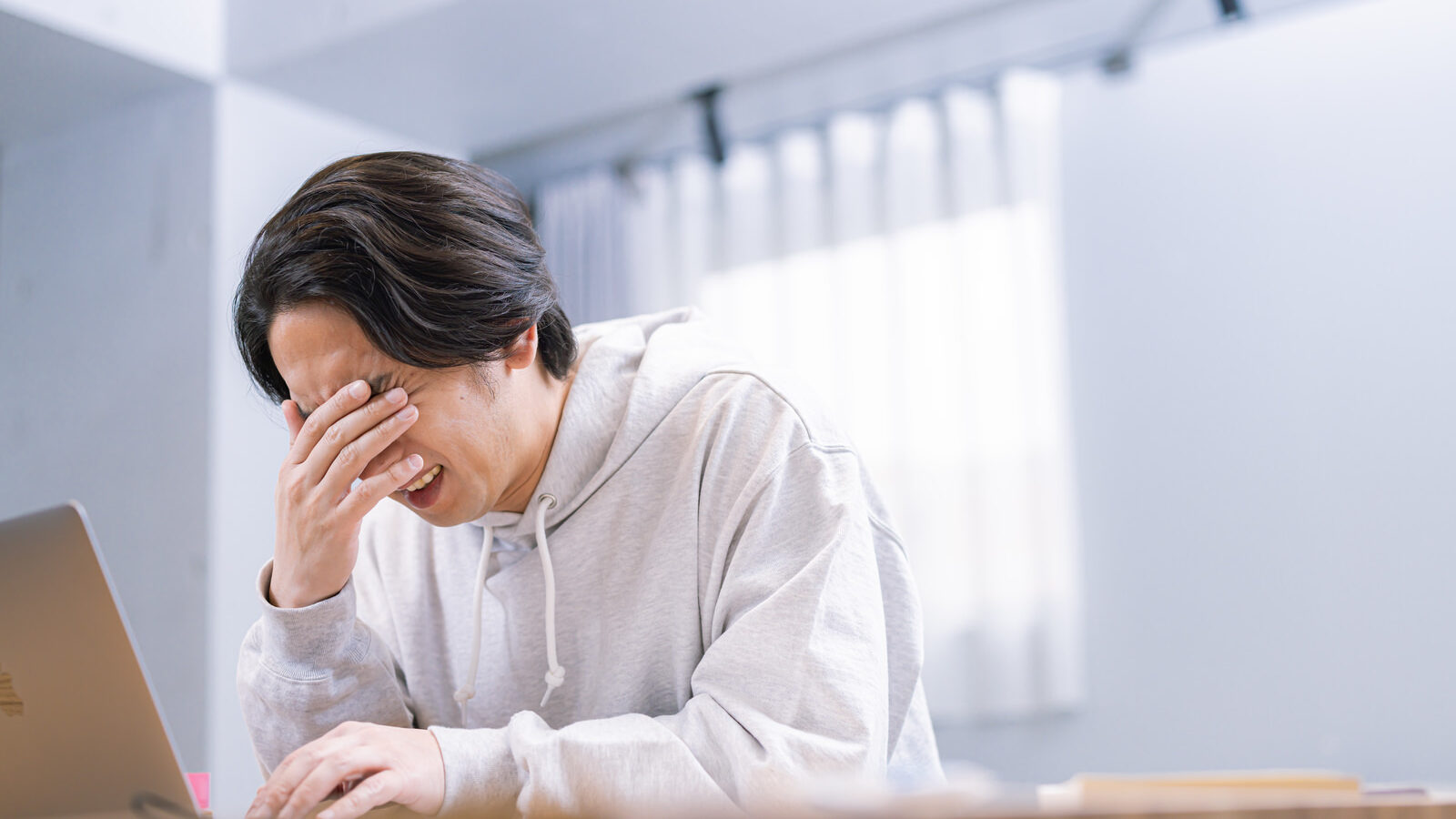2024年8月の植田ショック、2025年4月のトランプ関税ショックは記憶に新しいところですが、市場はそれらのイベントを乗り越えて2025年8月現在最高値圏を推移しています。私も一瞬含み益バリアが無くなりそうになる程度には削られました。
2024年1月に開始した新NISAで、初めて資産運用を始めた人の中には、あまりの相場の動きに委縮して積立の停止や口座の解約をしてしまった人も多いようですね。
投資信託の保有期間、長期化傾向が定着 – 日経新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL161510W4A410C2000000
長期積立を前提に、
- 積立設定さえしてしまえば、ほったらかしで資産形成が簡単にできる
- 短期的な値動きは長期の成績にほぼ影響を及ぼさない
- 暴落時こそ買い増し
など、「頭では」わかっていたはずなのに、いざ相場が急変動すると恐怖に支配されて逃げ出してしまうということは往々にあることです。
積立投資を継続するにはどうすればいいのか、銘柄を握り続ける握力を鍛えるにはどうすればいいのか考えてみました。
資産と現金の違い
投資初心者は、そもそも論として資産(ここでは投資商品としての意味合い)と現金の違いについての理解が不足している場合があります。
投資商品としての資産は多くの場合市場があり、日々値付けが変動します。不動産も価格の変動は緩やかですが、不動産市場がある以上(月単位~年単位で)価格は変動します。
対して、現金はそれ自体が勝手に増えたり減ったりするものではありません。
為替やインフレ的な側面から見れば現金自身の価値は変動しますが、今日の10,000円が1か月後には12,000円に勝手に増えたりはしません。
ただし、今日の10,000円は1年後も10,000円であり、今日10,000円で買えていたものが1年後には買えなくなっている可能性があることは要注意です。
この違いを認識せずにインデックスファンドや個別株を買うと、急に自分の財布から現金が出て行ったり入ってきたりするように錯覚します。
このため、投資初心者がまず実体験として覚えなければならないことは、日々の資産額の上下に慣れること、それにより減ったり増えたりしているのは財布の中の現金ではなく、資産額だという認識をもつことだと思います。
※売却すれば即現金になるため、実際にお金が出て行っているといえばその通りなのですが、ここでは現金の増減と資産の上下を区別することが重要と考えているのでご容赦ください。
行動経済学からの観点
ヤフオクやメルカリで、「これはいいものだから高く売れるだろう!」と思ったけど存外安い価格でしか売れなかったという経験がある人は少なくないかと思います。
自分の持っているものの価値を高く見積もってしまう効果を、行動経済学では授かり効果と呼ぶそうです。上記では売ってしまっていますが、本来は “高く価値を見積もっているため、手放したくないと考えること” だそうです。
この効果は相場の暴落時と非常に相性が悪く、
- 価値があると思って買ったはずが、どんどん値下がりしていく(見積りとのギャップ)
- 自分の見出した価値が正しいと思い込み、市場が間違っていると断定する(手放したくない)
- 下落に耐えられず損切りする(手放さざるをえなかった=意にそぐわない非常に大きな痛み、ストレス)
このような行動を引き起こすと考えられます。
積立投資は “ほったらかしでいい” ことは事実ですが、相場の急変時にも動揺せず続けるためには、このような行動経済学的効果を知っておくことも重要でしょう。
メンタルを鍛え、ホールド力を強化するには?
相場は動くものです。そして長期投資を行えば年率数%~10%以上で結果的に運用できる可能性も十分にあります。
しかし、インデックスファンドが有名になり、各証券会社等でも
「年率〇%で積み立て続ければ30年後にこれだけの資産になっていますよ~」
とあまりにもきれいすぎる曲線を出力していますが、半分は嘘みたいなものです。投資を続けていれば必ず何度も暴落に直面します。
ホールド力を強化するための本当に最初の一歩は、
- 資産額は変動するもの
- 真の意味で淡々と積立て、ほったらかしにする図太さをもつこと
これらが市場に生き残り続けるには必要なことだと思います。